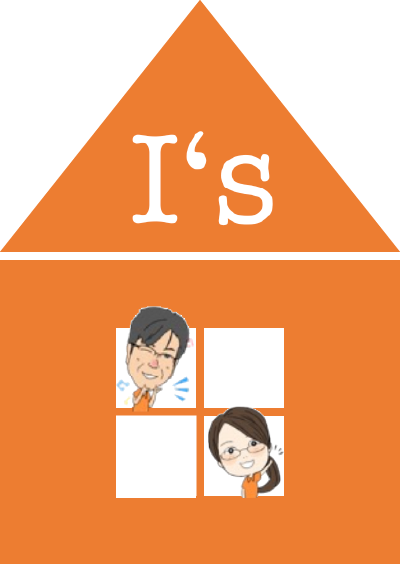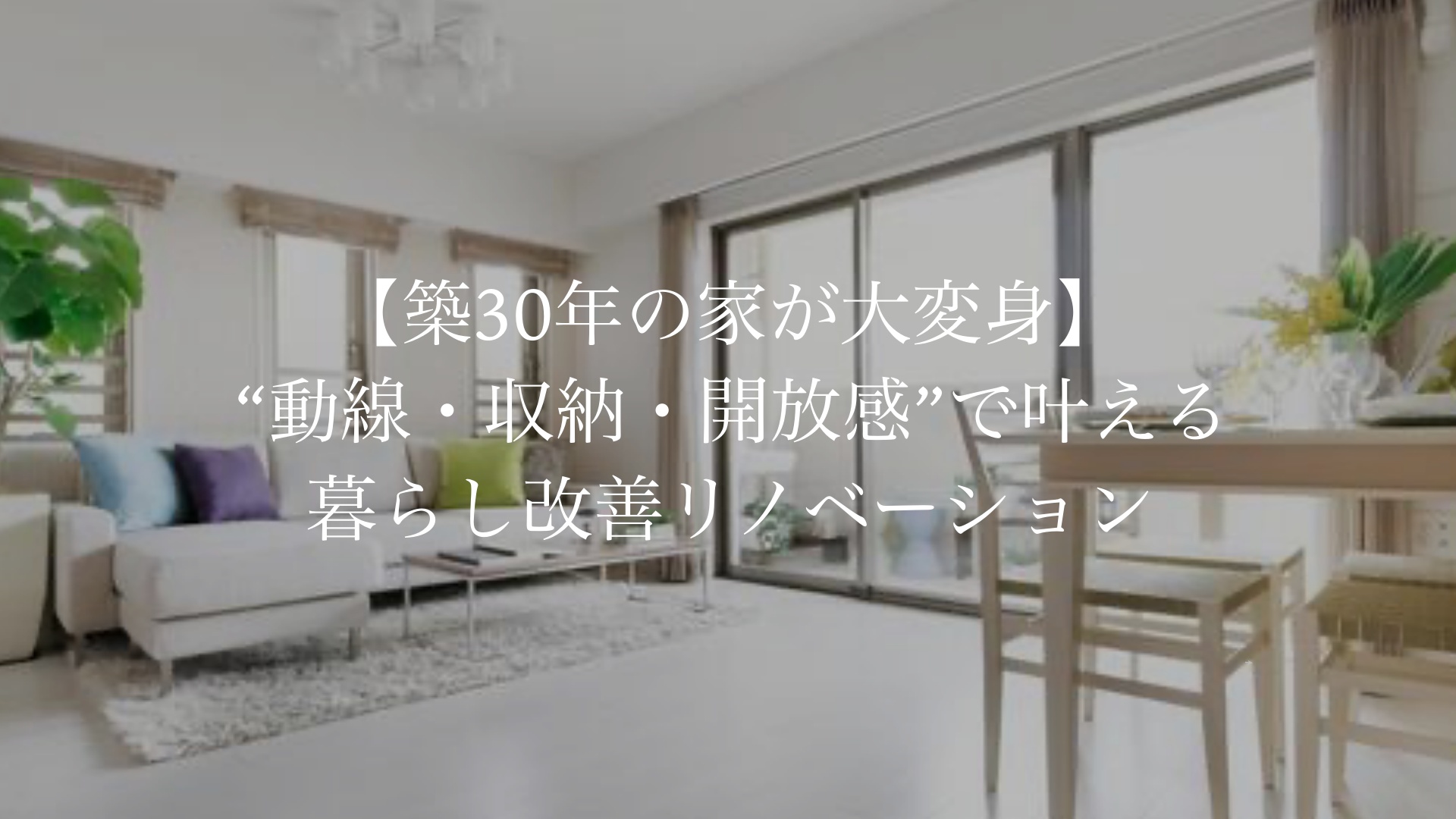
築30年の中古住宅を購入してリノベーションを考えているけれど、「間取りってどこまで変えられるの?」「昔の家って家事動線が悪そう…」そんな不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
30年前の住宅には、当時の生活スタイルや建築常識に基づいた設計が施されているため、現代の暮らしに合わない点が多く見られます。たとえば、キッチンが独立していて家族との会話がしづらかったり、押入れ中心の収納で使い勝手が悪かったり、廊下が長くて無駄な空間が多かったり…。
そこで今回は、【動線】【収納】【開放感】という3つの観点から、築30年の間取りを快適に再構築するリノベーションの工夫をご紹介します。これからリノベを検討される方に向けて、現代の暮らしにフィットする家づくりのヒントをお届けします。
築30年の住宅にありがちな間取りの悩みとは?
昔の住宅には、今では考えられないような“使いにくさ”が多く残されています。ここでは、築30年の住まいに見られる典型的な課題を整理してみましょう。
孤立したキッチンで家事がしづらい
昔の住宅では、キッチンが壁に囲まれた独立型で設計されていることが多く、リビングやダイニングとの視線や動線が分断されています。
その結果、料理中に家族とコミュニケーションをとることが難しくなり、特に小さなお子様がいるご家庭では、様子を見守りながら調理をすることができず不安を感じる場面もあります。また、配膳や片付けのたびに何度も往復が必要になるなど、家事効率の面でも不利な構造となっています。

押入れ中心の収納では使い勝手が悪い
収納といえば押入れ、という時代。和室に設けられた押入れは、布団の収納を前提とした奥行きが特徴的で、奥に入れた物が取り出しにくく、しまい込んだまま使わなくなる“死蔵品”になってしまうケースも少なくありません。
また、棚板の構造が単純で上下の空間が無駄になりがちであり、高さ調整が効かないことも多く、日用品や家電、衣類といった現代の多様な収納ニーズには対応しづらい構造です。
加えて、リビングや玄関近くなど、必要な場所に十分な収納が確保されていないため、片付けの動線が悪く、日常的に散らかりやすくなる要因にもなります。

廊下が多くてスペースが無駄に見える
居室をつなぐために長い廊下を設ける間取りが主流だったため、家の中に“通るだけの空間”が多く存在してしまう傾向があります。
廊下は居室の独立性を高める反面、居住空間としての機能を果たさないため、限られた床面積を有効活用できず、実質的な生活スペースが狭くなってしまいます。また、照明や空調などの設備を考慮すると、維持コストの面でも効率が悪く、特に小さな家では空間配分の見直しが求められます。
現代のリノベーションでは、このような廊下を極力減らし、動線を集約した“通りながら使える空間”へと変える工夫が増えています。

“家事ラク”動線を実現する間取りリノベの工夫
リノベーションで動線が改善されると、毎日の生活が大きく変わります。無駄な動きが減り、家事のストレスが軽減される間取りの工夫を紹介します。
キッチン〜洗面〜物干し場を一直線にする
料理・洗濯・掃除といった家事は、住宅内での移動が多く、それぞれが別々の場所にあると、家事をこなすたびに行ったり来たりしなければならず、大きな負担になります。特に、キッチンで食事の準備をしながら洗濯機を回し、さらに洗濯物を干しに行くといった一連の動作において、移動距離が長いと効率が悪く、時間も体力も無駄にしてしまいます。
そこで、キッチン・洗面・物干し場といった“家事スポット”を一直線に配置することで、動線が最短化され、複数の家事を並行して進めることが可能になります。この配置は特に共働き家庭や子育て世代にとって、毎日の生活の中でその効果を実感しやすい重要な設計ポイントです。

回遊動線をつくって「行き止まり」をなくす
リビング・ダイニング・キッチンを回遊できるようにすれば、生活動線がスムーズになり、家の中の移動が格段にしやすくなります。
たとえば、朝の忙しい時間帯に家族全員が同じ場所を通ると、すれ違いや渋滞が起きやすくなりますが、回遊動線を確保することで一方向だけでなく、複数のルートから移動できるため、動きがぶつからず、快適に行き来ができます。
また、料理をしながら子供の様子を見守ったり、リビングから洗面所へとスムーズにアクセスできるなど、複数の家事や育児を並行して行う上でも効率的です。
とくに小さなお子様がいるご家庭では、安全性の面でも大きなメリットがあり、親がどこにいても子供の動きを把握しやすくなる設計といえます。

脱衣室と洗濯室を分けて家事効率UP
洗濯機がある脱衣所は、他の家族が入浴している間は使いづらく、洗濯作業が一時的に中断されてしまうという不便さがあります。
たとえば、「お風呂に誰かが入っているから洗濯ができない」「着替えを取りに入れない」といったシーンは、日常の中で意外と多く見受けられます。特に共働き家庭や子育て世帯では、家事を“隙間時間”で効率よくこなしたいときに、このような動線の干渉がストレスになりがちです。
そこで、脱衣室と洗濯室を物理的に分ける間取りにすることで、誰かが入浴していても洗濯は滞りなく進められ、洗濯物の取り出しや干す作業もスムーズに行えます。
また、洗濯専用のスペースを設けることで、アイロンがけやたたむ作業のスペースも確保しやすくなり、洗濯に関する一連の作業がその場で完結する“家事の集約化”にもつながります。

“収納力”が家の快適さを左右する
収納は「量」だけでなく、「場所」「使いやすさ」が非常に重要です。
いくら大きな収納スペースがあっても、生活動線から遠かったり、必要な時にすぐ取り出せない場所にあると、かえって不便になってしまいます。たとえば、掃除用具が寝室の奥にしかない、よく使う文具が2階にしかないといった状況では、日常的な行動がスムーズにいきません。
また、使う場所の近くに適切な収納があると、物の出し入れがしやすくなり、自然と片付けが習慣化しやすくなります。さらに、家族全員が使いやすい高さや大きさであることもポイントです。
生活スタイルに合わせて、「何を・どこで・どのように」収めるかを事前に計画することで、収納は単なる“空間”から“暮らしを支える仕組み”へと進化します。これにより、家全体がすっきりと整い、快適な住環境が実現できるのです。

ファミリークローゼットで“集約型”にする
家族全員の衣類をまとめて一か所に収納できるファミリークローゼットは、収納スペースを“分散”させずに“集約”することで、家事の効率を大幅に高めることができます。
たとえば、洗濯を終えた後に、それぞれの部屋に衣類を持っていく手間が省け、収納も一括で済ませられるため、家事動線がシンプルになります。
また、子どもが小さいうちは一緒に服を選んだり、着替えの手伝いがしやすくなりますし、年齢を重ねても「自分で服をしまう・選ぶ」といった自立の習慣を育てる場としても有効です。
配置のポイントとしては、リビングや洗濯機のある洗面脱衣室からアクセスしやすい場所に設けること。動線が短くなることで、日々の家事がぐっと楽になります。
玄関・廊下・階段下を“隠れ収納”に活用
デッドスペースになりがちな玄関脇や廊下、階段下は、普段あまり意識されないものの、実は収納に活用できる非常に貴重な空間です。
これらの場所は構造的に制約があるため、活用されずに“空白のエリア”として放置されがちですが、目的を絞った収納を設けることで、家全体の収納力を底上げすることができます。
たとえば、玄関脇には靴や傘だけでなく、子どもの外遊び道具やアウトドア用品、消耗品のストックなどを収納できます。また、廊下の壁面や階段下の空間は、掃除機やモップなどの掃除道具、防災用品、季節家電の一時保管場所として非常に適しています。
さらに、扉付きの収納を設ければ生活感を抑えることができ、見た目の美しさも保てます。こうした“隠れ収納”は、ちょっとした工夫と設計によって、暮らしの質を高める重要な役割を果たします。
“見せる収納”と“隠す収納”を住み分ける
おしゃれな棚にお気に入りの雑貨やグリーン、小物などを飾る“見せる収納”は、空間に個性とアクセントを加え、暮らしの豊かさや趣味の表現にもつながります。一方で、掃除道具や生活雑貨、日用品のストックなど“生活感のある物”は扉付きの棚や収納ボックスなどでしっかりと“隠す収納”に収めることで、空間の乱雑さを防ぐことができます。
この2つの収納をバランスよく併用することで、視覚的にすっきりとした印象と、使い勝手のよさを両立することができ、室内に自然なメリハリが生まれます。特にリビングやダイニングのような人目に触れる場所では、こうした収納の“見せ方・隠し方”を意識することが、空間全体の印象を左右します。
“開放感”を演出する空間リノベのポイント
狭くても広く感じられる工夫は、設計次第でいくらでも実現可能です。視線の抜け方や天井の高さなどに注目しましょう。

天井高を上げる or 勾配天井で抜け感を出す
天井の高さは、空間に対する心理的な広がりや解放感に大きな影響を与える要素です。
一般的な天井高は2.4m程度ですが、これを少し上げるだけでも圧迫感が減り、空間に余白を感じさせることができます。さらに、屋根の傾斜を活かした勾配天井を取り入れることで、視線が斜め上に抜け、より開放的でドラマチックな空間演出が可能になります。
梁を現しにすることで、天井に奥行きや陰影が生まれ、木の質感を活かしたナチュラルな雰囲気や、ヴィンテージ感のある空間にも仕上がります。
また、勾配天井は高窓(ハイサイドライト)や天窓との相性も良く、自然光を効果的に取り込むことで、昼間の照明使用を抑えるエコな設計にもつながります。
限られた床面積でも「高さの使い方」で空間に奥行きと快適性を持たせることができるため、天井デザインの工夫はリノベーションにおいて非常に有効な選択肢のひとつです。
間仕切りを減らして“LDK一体化”
壁を取り払ってリビング・ダイニング・キッチン(LDK)をひとつの空間にまとめることで、圧迫感のない開放的なレイアウトが実現できます。
各部屋が独立していた従来の間取りでは、部屋ごとに仕切られて視線や動線が遮断され、家族が同じ家にいながらも“孤立感”を感じやすい状況になりがちでした。
LDK一体型の空間では、調理中にリビングにいる子どもと会話したり、ダイニングで作業する家族と自然にやりとりができたりと、日常の中で生まれる“ちょっとした交流”が増えます。
また、空間が一体化していることで照明や冷暖房の効率も高まり、省エネ効果も期待できます。特に限られた床面積の住まいにおいては、壁を取り除くだけで広さ以上の“広がり感”が演出できるのが大きなメリットです。
視線が抜ける「抜け道線」のつくり方
空間の先に窓や庭が見えるように家具や壁の配置を工夫することで、視線の抜けが生まれ、部屋に“奥行き”を感じさせることができます。これは視覚的な広がりを演出する有効な手法で、実際の床面積以上に空間が広く感じられる効果があります。
たとえば、リビングの先に掃き出し窓を設けて外の庭やテラスが見えるようにすれば、内と外が自然につながり、圧迫感のない心地よい空間になります。
また、このような配置は自然光の取り込みにも非常に効果的で、日中は照明に頼らなくても明るく、時間帯によって変化する光の表情を楽しむことができます。結果として、開放感と快適性を両立した空間づくりに繋がります。
間取りリノベを成功させるための注意点
どんなリノベも自由にできるわけではありません。計画前に押さえておきたい注意点をまとめました。

構造上抜けない壁に要注意
耐力壁とは、建物の構造を支える重要な役割を担っている壁のことです。このような壁は地震や風圧などの外力に耐えるために設けられており、安易に撤去してしまうと建物全体の強度が低下し、非常に危険です。
そのため、間取りの変更を行う際には、まず既存の壁が構造上どのような役割を持っているのかを専門家が調査・診断する必要があります。リノベーションでは、「この壁を取り払えば開放感が出る」といった要望も多いのですが、耐力壁であれば撤去できないか、または構造補強を施してからでないと変更ができません。
このような判断には建築士や構造の専門家の知見が不可欠です。設計の自由度を確保しつつも、安全性と耐震性を損なわないよう、慎重な計画とプロの判断をもとに進めることが大切です。
耐震・断熱の性能アップも並行して検討
間取り変更を行う際は、壁や床を一度解体する必要があるため、通常では手が届きにくい箇所の性能改善にも取り組む絶好の機会となります。
特に断熱材の入れ替えは、築30年以上の住宅において非常に効果的です。当時の断熱基準は現代と比較すると大きく異なり、外気の影響を受けやすく、夏は暑く冬は寒いといった住環境の課題が生じやすくなっています。最新の高性能断熱材を採用することで、室温の安定性が向上し、冷暖房費の節約や快適性の大幅な向上が期待できます。
また、耐震補強についても、現在の耐震基準を満たしていない建物に対して、壁の補強や金物の追加といった改修を行うことで、地震への備えが強化されます。特に、開口部の位置を変えるなど構造的な変化を伴うリノベーションでは、構造計算を行ったうえで耐震性の再評価と補強を行うことが推奨されます。
このように、間取り変更は単なるデザイン刷新にとどまらず、「住まいの性能そのものを底上げする」絶好の機会でもあるのです。
固定資産税や建築確認の確認も忘れずに
大規模な間取り変更を行う際には、その内容によっては建築基準法上の「増築」と見なされる可能性があります。たとえば、部屋を増やす、天井を高くする、ロフトを設ける、バルコニーを囲って室内にするなど、建物の床面積や容積に影響を与える工事は、確認申請が必要となるケースが多くなります。
また、容積率・建ぺい率といった土地の法的制限を超えてしまうと、そもそも工事が許可されない場合もあるため、設計前にしっかりと現地調査・法令チェックを行う必要があります。
さらに、固定資産税の課税対象面積が増えることで、税額が上がる可能性もあるため、コスト面でも注意が必要です。こうした法的・制度的な確認を怠ると、完成後に是正指導や使用制限を受けるリスクもあるため、事前に建築士や行政窓口へ相談することが重要です。
まとめ
築30年の中古住宅でも、間取りの工夫とリノベーションによって、現代の暮らしに合った快適な住まいへと生まれ変わります。
「家事動線」「収納」「開放感」という3つの視点で見直すだけで、毎日の暮らしがぐっとラクに、そして楽しくなるはずです。
リノベーションをお考えの方は、ぜひこれらのポイントを参考に、理想の住まいづくりにチャレンジしてみてください。

信頼関係が大切
家づくりには担当者との信頼関係がとても大切です!
性能が良い、デザインが良い、安いから、なんて理由ではなく、何十年先も付き合っていく住宅会社、担当者として見た時に「安心できるな」と思った会社を選びましょう!
あなたを理解し、良いことも悪いこともちゃんと伝えてくれる人。
我慢するばかりではなく、この人なら何とかしてくれると思える人。
そんな信頼できる住宅会社と担当者を探すことがとっても大切なのです。
株式会社アイズホーム
建築士とともにあなたに寄り添った家づくり
お問い合わせはこちら
https://is-h.jp/inquiry
アイズホームでは、そんなご家族様一人ひとりの想いに寄り添った家づくりをお手伝いしております。
浜松市で新築をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。