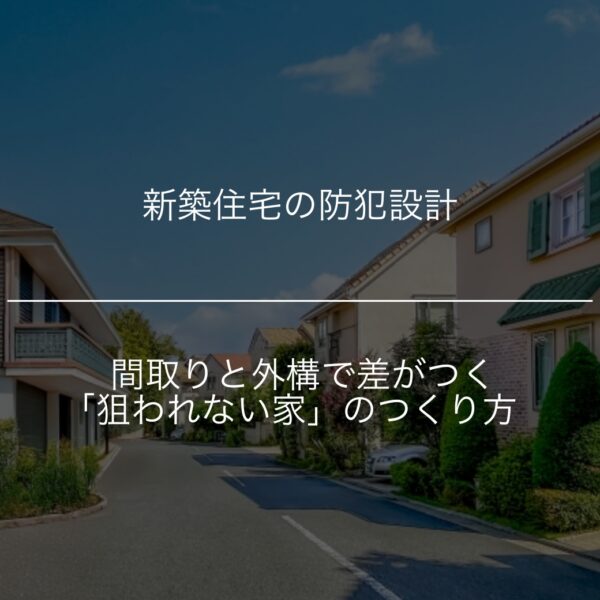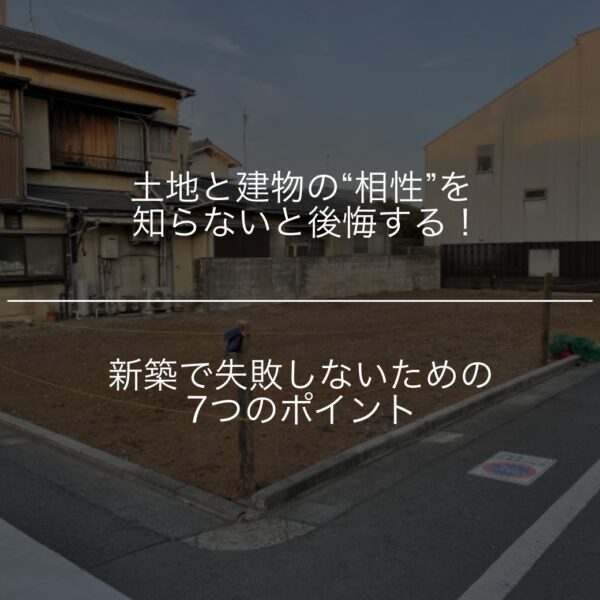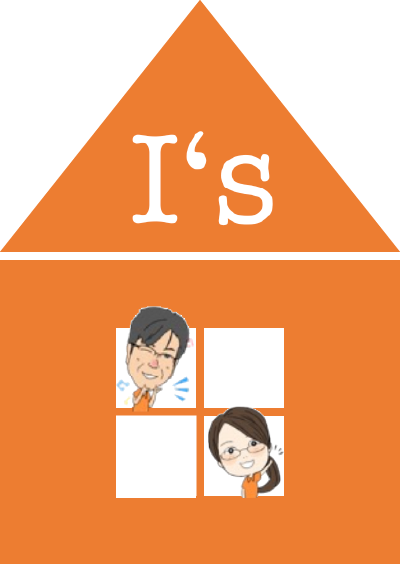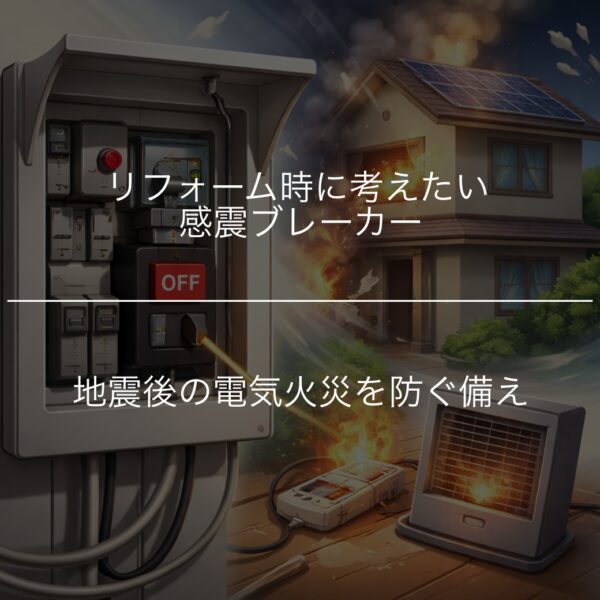
大きな地震が起きたとき、多くの方がまず思い浮かべるのは「建物が倒れないか」という不安ではないでしょうか。しかし実際には、地震そのものよりも、その後に発生する火災によって被害が拡大するケースが少なくありません。特に問題とされているのが、停電から復旧した際に起こる「通電火災」です。
近年の大規模地震でも、電気機器や配線が原因とみられる火災が多く報告されています。倒れた電気ストーブに再び電気が流れたり、損傷したコードがショートしたりすることで、思わぬ出火につながるのです。こうしたリスクは、新築住宅だけでなく、築年数を重ねた既存住宅ではさらに高まると考えられています。
リフォームを検討されているご家庭にとって、耐震補強や断熱改修、水回りの更新はもちろん重要ですが、「地震のあとに火事を起こさないための備え」まで考えられている方は、まだ多くありません。そこで注目されているのが、地震の揺れを感知して自動的に電気を遮断する「感震ブレーカー」です。
この記事では、リフォーム住宅における電気火災のリスクと、その対策としての感震ブレーカーについて、仕組みや導入方法、注意点をわかりやすく解説します。これからリフォームを予定されている方が、後悔のない防災対策を考えるきっかけになれば幸いです。
リフォーム住宅で高まりやすい電気火災のリスク
リフォームを検討する背景には、「家が古くなってきた」「設備の不具合が気になる」といった理由が多くあります。実は、こうした状態の住宅ほど、地震後の電気火災リスクが高くなる傾向があります。
築年数が経過した住宅では、配線やコンセントが長年使用されてきたことで劣化している場合があります。また、生活スタイルの変化により、延長コードやタコ足配線が増えているご家庭も少なくありません。これらは平常時には問題なく使えていても、地震による揺れで破損し、通電した瞬間に火災につながる恐れがあります。
さらに、地震直後は停電が発生することが多く、「電気が止まっているから大丈夫」と思いがちです。しかし、復旧時には人がいない時間帯や就寝中に突然通電することもあり、気付かないうちに火が出てしまうケースも想定されます。このような背景から、リフォーム住宅では耐震性だけでなく、電気火災への備えも同時に考えることが大切です。

感震ブレーカーとは?仕組みを解説
感震ブレーカーとは、一定以上の強い揺れを感知すると、自動的に電気を遮断する装置のことです。一般的には震度5強程度の揺れで作動するよう設定されており、地震発生時に分電盤やコンセントの電気を止める役割を果たします。
最大の特徴は、停電が復旧した後も、利用者が手動で操作しない限り電気が再び流れない点です。これにより、倒れた電気ストーブや損傷した配線に知らないうちに通電してしまう事態を防ぐことができます。
感震ブレーカーにはいくつかの種類があり、分電盤に取り付けるタイプのほか、工事不要で設置できる簡易型もあります。難しい操作が不要なため、高齢のご家族がいらっしゃるご家庭や、留守が多いご家庭でも取り入れやすい防災対策といえるでしょう。

リフォーム内容別に考える感震ブレーカーの導入方法
感震ブレーカーは、すべての住宅に同じ方法で設置すればよいというものではありません。リフォームの内容に応じて、適した導入方法を検討することが重要です。
分電盤の交換や電気設備の更新を伴うリフォームの場合は、分電盤に後付けするタイプの感震ブレーカーを検討しやすくなります。この場合、電気工事と同時に設置できるため、工事の手間を抑えながら防災性能を高めることができます。
一方で、水回りの改修や内装リフォームなど、電気工事をほとんど行わない場合でも、工事不要の簡易型感震ブレーカーという選択肢があります。おもりやバネの仕組みでブレーカーを落とすタイプで、比較的手軽に導入できる点が特徴です。
このように、ご家庭の状況やリフォーム内容に合わせて選ぶことで、無理のない防災対策につなげることができます。

既存住宅向けに広がる補助制度と注意点
感震ブレーカーの普及を進めるため、自治体によっては設置費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。特に、木造住宅が密集する地域や既存住宅を対象とした制度が中心となっている点が特徴です。
ただし、補助の内容や対象条件は自治体ごとに異なり、事前の申請が必要なケースも少なくありません。リフォーム工事を始めてからでは利用できない場合もあるため、計画段階で確認しておくことが大切です。
また、感震ブレーカーを設置すると、地震時には建物全体が停電状態になります。そのため、非常用照明や懐中電灯の準備など、停電時の備えもあわせて考えておく必要があります。防災対策は一つだけで完結するものではなく、複数の備えを組み合わせることが安心につながります。

まとめ
リフォームは、住まいを快適に整えるだけでなく、安全性を見直す大切な機会でもあります。地震対策というと耐震補強に目が向きがちですが、地震後に発生する火災への備えも欠かせません。
感震ブレーカーは、地震の揺れをきっかけに電気を遮断し、通電火災のリスクを抑えるための現実的な対策です。リフォームの内容やご家庭の状況に合わせて導入を検討することで、無理なく防災性能を高めることができます。
これからリフォームを予定されている方は、間取りや設備だけでなく、「もしものときに火事を防げるか」という視点も取り入れてみてはいかがでしょうか。その一つの選択肢として、感震ブレーカーを検討することが、安心できる住まいづくりにつながります。

住宅ローン借り換え相談会
(リフォームローン相談会も同時開催してます!)
毎月の返済をもっとラクに、将来の安心を手に入れませんか?
毎月の支払い、少しでも軽くできたら…
「住宅ローンの返済が家計の大半を占めている」
「金利が上がるニュースを見ると不安になる」
そんなお声を最近よく耳にします。
実は、今のローンを“見直す”だけで月々1万円以上支払いが軽くなるケースも珍しくありません。
さらに、総返済額が100万円以上変わることもあるのです。
今回開催する「住宅ローン借り換え相談会」では、
専門の住宅FPが今の金利・将来の金利動向・あなたのライフプランをもとに、
最適な返済プランをご提案いたします。
無理な勧誘は一切ありません。
「うちも借り換えたほうがいいのかな?」と気になったタイミングで、
お気軽にご参加ください。
【こんな方におすすめです】
-
月々の支払いを少しでも減らしたい方
-
固定金利から変動金利に変えるか迷っている方
-
変動金利のままで大丈夫か不安な方
-
住宅ローンを組んでから5年以上経っている方
-
教育費や老後の資金も考えて、将来に備えたい方
「今のローン内容を見直したいけれど、どこに相談したらいいかわからない…」
そんな方にこそ、一度参加していただきたい相談会です。
【相談会でわかること】
-
いま借り換えをするべきかどうか
→ 金利だけでなく、保証料・諸費用も含めて「得か損か」を数値で比較します。 -
どの銀行・金利タイプが合っているか
→ メガバンク、ネット銀行、地方銀行などを比較し、あなたに最適な選択を一緒に考えます。 -
将来の家計にどんな影響があるか
→ 教育費や老後資金のシミュレーションも行い、安心して返済を続けられるかを確認します。 -
借り換え以外の選択肢
→ 繰上返済・金利タイプ変更・返済期間の見直しなど、他の手段もアドバイスします。
【相談会の流れ】
-
ご予約
お電話でのご予約ですとスムーズにご案内できます。
フリーダイヤル:0120-806-006 -
下記URLよりフォームにて、ご希望の日時を選択してお申し込みください。
(平日・土日とも開催。お子様連れでもOKです) -
ヒアリング
現在のローン内容や家計の状況をお伺いします。
事前にローン明細や金利のわかる書類をご準備いただくとスムーズです。 -
シミュレーション
金利差・期間・諸費用をもとに、借り換え後の毎月の返済額を具体的に比較。
「どれだけ変わるのか」が一目でわかります。 -
アドバイス・質疑応答
あなたのライフプランに合わせた最適な返済方法をご提案します。
無理に借り換えを勧めることはありません。安心してご相談ください。
【参加者の声】
「思っていたよりも簡単にシミュレーションできて驚きました!」
「ネット銀行の方が安いと思っていましたが、意外な結果に!」
「教育費とのバランスを見直すきっかけになりました」
多くの方が「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃいます。
住宅ローンは“長く付き合うもの”だからこそ、定期的な見直しが大切です。
【開催概要】
-
開催日:毎週土日(平日をご希望の方はご相談ください)
-
時間:10:00〜17:00(1組60分〜90分)
-
会場:アイズホーム本社事務所
〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北3丁目1-17 -
参加費:無料(完全予約制)
-
持ち物:ローン返済予定表・源泉徴収票(任意)
※お子様と一緒のご来場も大歓迎です。
【お申し込みはこちら】
以下のフォームに必要事項をご入力ください。
折り返し、スタッフより日程確認のご連絡を差し上げます。
お問い合わせフォーム:https://is-h.jp/inquiry
ご希望日時(第1〜第3希望まで)
お問い合わせフォームの詳細記入欄にご希望日時(第1〜第3希望まで)をご記載ください。
\ まずはお気軽にご相談ください! /
【最後に】
住宅ローンの借り換えは、「家計の見直し」と「将来の安心」を得るチャンスです。
何となく不安を感じながら過ごすよりも、
一度プロに相談して“現状を知ること”から始めてみませんか?
あなたとご家族様が、安心して笑顔で暮らせる未来のために。
私たちはその第一歩をサポートいたします。