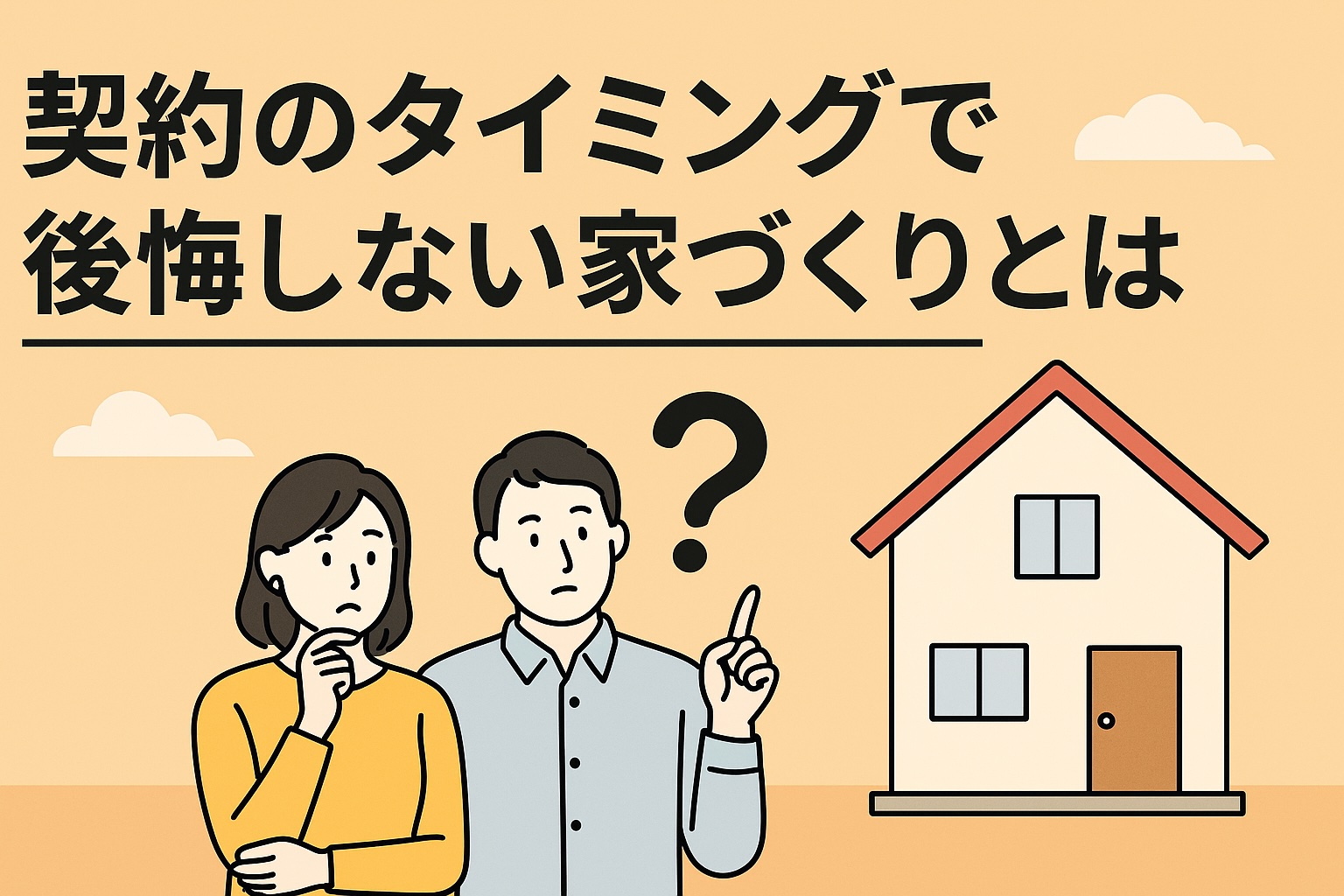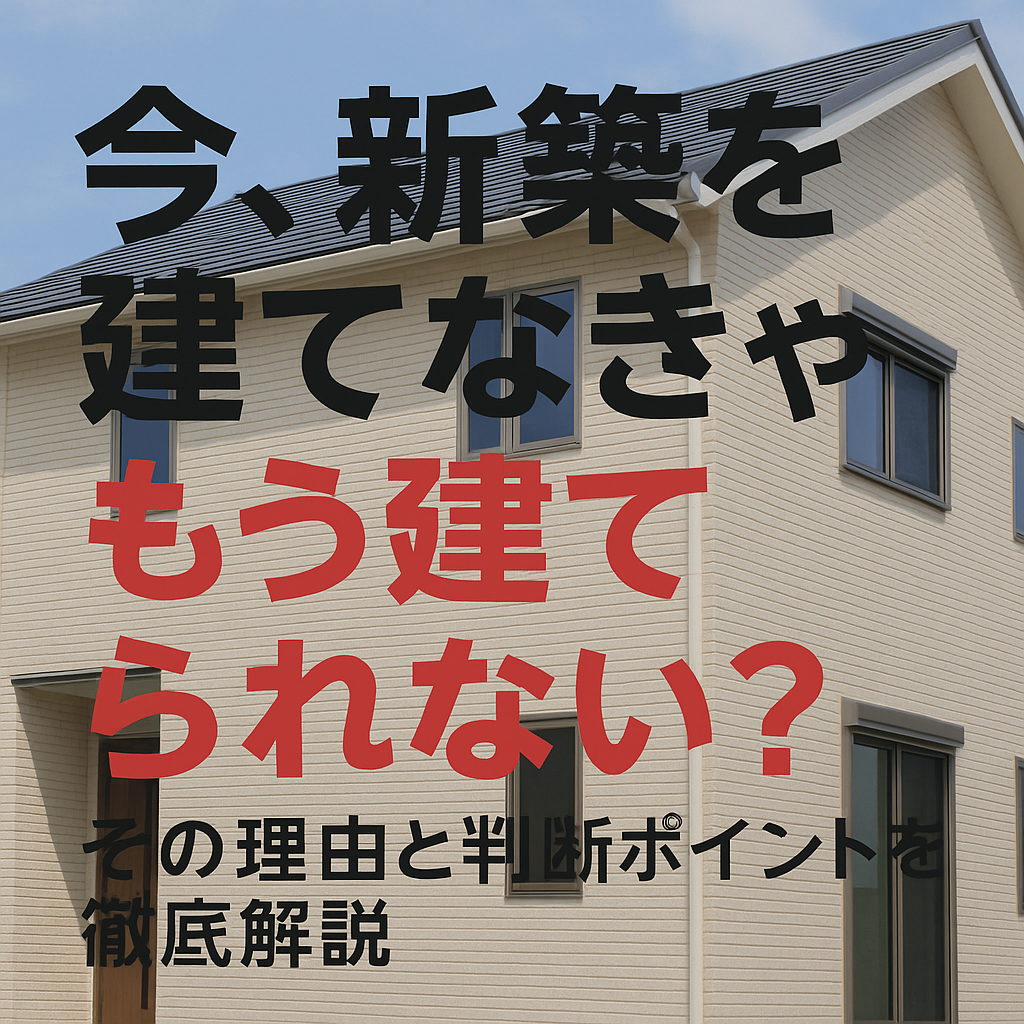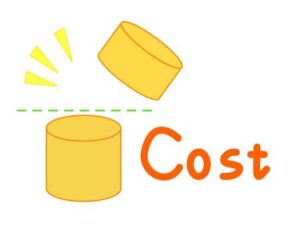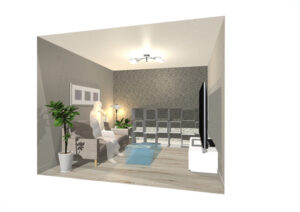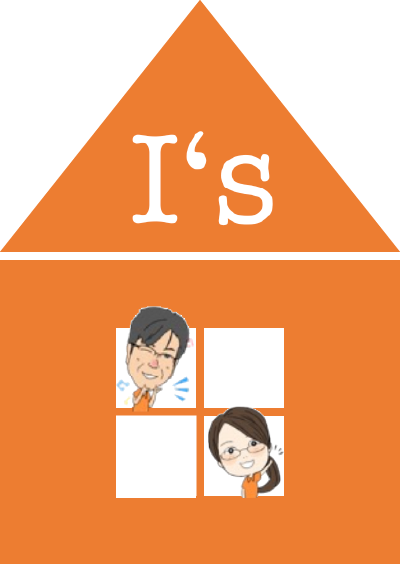家づくりは人生の一大イベント。だからこそ「絶対に後悔したくない!」と誰もが思うはずです。しかし実際には、完成後に「こうしておけばよかった…」と悔やまれるケースも少なくありません。前回の記事では、注文住宅で失敗してしまう方のよくある行動のうち、2つのポイントをお伝えしました。今回はその続きとして、3つ目・4つ目のポイントをご紹介いたします。
見た目の印象や大手ブランドへの安心感に惹かれる気持ちはよく分かりますが、目に見えない部分こそが、住まいの満足度を大きく左右します。建てる前だけでなく、「建てた後」にも目を向けることが、後悔しない住まいづくりへの第一歩です。
この記事を通して、信頼できるパートナーと出会い、本当にご家族に合った家づくりができるよう、少しでも参考になれば幸いです。
大手ハウスメーカーなら安心?その思い込みにご注意を
「大手なら安心」「ネームバリューがあるからきっと大丈夫」。そう思って家づくりを進めてしまう方は意外と多いものです。
もちろん、大手ハウスメーカーが悪いわけではありません。建物の品質や技術面では優れている部分も多く、魅力的な商品を展開している会社もあります。しかし、「大手だから良い家に決まっている」と信じ込み、他社と比較検討をしないまま契約してしまうのは非常にリスクが高い行動です。
大手の住宅会社は、広告や展示場などに大きなコストをかけているため、住宅の販売価格も高めに設定されていることが多くなります。また、営業担当者は「家を売るプロ」であって、「家をつくるプロ」ではないケースもあるため、詳しい設計や工法についての理解は限定的な場合も。
こうした背景を理解したうえで、「価格と性能」「ライフスタイルとの相性」「柔軟な対応力」などを総合的に見て、地元の工務店なども含めてしっかりと比較することが大切です。
特に、「価格が高い=理想の暮らしが手に入る」と思い込んでしまうと、本当に必要な間取りや動線設計を後回しにしてしまうこともあります。理想の暮らしを実現するためには、規模やブランドだけに惑わされず、本当に自分たちに合った家を提案してくれる会社を選ぶ視点が必要です。

デザイン重視だけではダメ?「見た目以上に大切なこと」とは
「かっこいい家に住みたい」「おしゃれな家を建てたい」。そんな願いを持つのは当然のことですし、とても素敵なことだと思います。ご家族の趣味や好みに合ったデザインは、日々の暮らしをより楽しく、豊かにしてくれます。
しかし、「見た目だけ」で判断してしまうのは危険です。
どんなに外観が素敵でも、**建てた後のサポート体制や信頼関係が不十分だった場合、満足度は一気に下がってしまいます。**実際にこんな事例もありました。
■ 大手ハウスメーカーの事例
誰もが知る大手住宅会社で家を建てた方。入居後に不具合が見つかり、すぐに電話をかけて相談しました。電話口では「担当者に伝えます」と丁寧な対応。しかし、3日経っても連絡はなし。再度電話をすると、また同じ回答。そしてさらに3日…最終的に担当者から「忘れていた」と言われ、対応に来たのは初回の電話から10日後だったそうです。
■ 地元工務店の事例
地元で信頼されている工務店に建築を依頼したお客様。数年後に雨漏りが発生し、連絡をしたところ、一度は対応日が決まったものの、何度も約束が破られ、結果的に1年もの間、放置されてしまったとのこと。
このような実話は決して珍しくありません。「信頼して任せたのに、こんなことになるなんて…」という後悔が、一生の買い物を苦い思い出にしてしまうのです。
だからこそ大切なのは、建てる前の見た目だけではなく、「建てた後もきちんと寄り添ってくれる会社かどうか」を見極めること。
信頼できる住宅会社は、引き渡し後の点検・メンテナンスも丁寧に対応し、トラブル時にも迅速に連絡が取れる体制を整えています。契約時の対応だけでなく、「長く付き合える相手かどうか」を見抜く目を養うことが何より大切です。

家づくりで大切なのは「信頼関係」
これまでお伝えした通り、家づくりは見た目やブランドだけではなく、「建てた後の安心感」「信頼関係」がとても重要です。
住宅は完成した瞬間がゴールではなく、そこからが新たなスタート。だからこそ、「どんな会社が建てるか」「その担当者がどれだけ親身になってくれるか」が、家づくりの満足度に大きく関わってきます。
アイズホームでは、「感動と笑顔あふれる家づくり」を合言葉に、建てた後もお客様とのつながりを大切にしています。当たり前のことを、当たり前に続けていく。そんな誠実な姿勢で、お客様と一緒に理想の住まいを育てていきたいと考えています。

まとめ:信頼できるパートナーと出会うことが、後悔しない家づくりの第一歩
注文住宅を成功させるカギは、「情報の多さ」ではなく、「信頼できる人と出会えるかどうか」です。
-
ブランド名に安心して、比較検討を怠らないこと
-
見た目だけにとらわれず、建てた後のフォローまで見極めること
-
自分の理想の暮らしを叶えてくれる設計力があるかを見抜くこと
-
担当者との信頼関係を築けるかを重視すること
これらのポイントをしっかり押さえることで、後悔のない家づくりに近づいていけるはずです。
アイズホームでは、初めてのご相談から家づくり後のサポートまで、お客様の立場に立ったご提案と対応を大切にしています。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

信頼関係が大切
家づくりには担当者との信頼関係がとても大切です!
性能が良い、デザインが良い、安いから、なんて理由ではなく、何十年先も付き合っていく住宅会社、担当者として見た時に「安心できるな」と思った会社を選びましょう!
あなたを理解し、良いことも悪いこともちゃんと伝えてくれる人。
我慢するばかりではなく、この人なら何とかしてくれると思える人。
そんな信頼できる住宅会社と担当者を探すことがとっても大切なのです。
株式会社アイズホーム
建築士とともにあなたに寄り添った家づくり
お問い合わせはこちら
https://is-h.jp/inquiry
アイズホームでは、そんなご家族様一人ひとりの想いに寄り添った家づくりをお手伝いしております。
浜松市で新築をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。