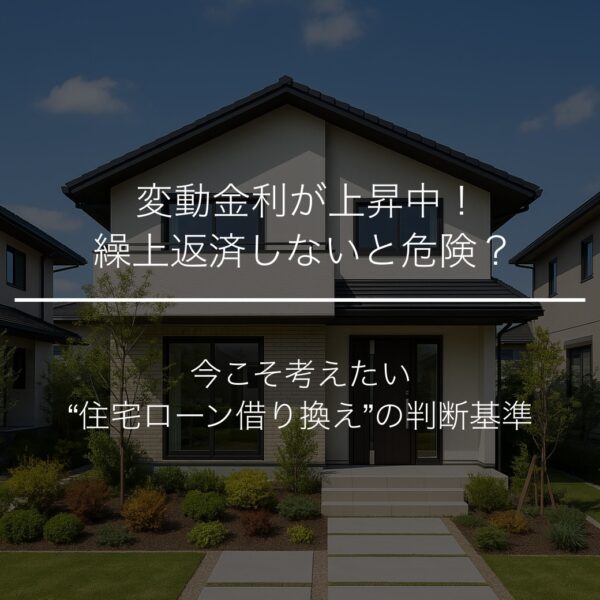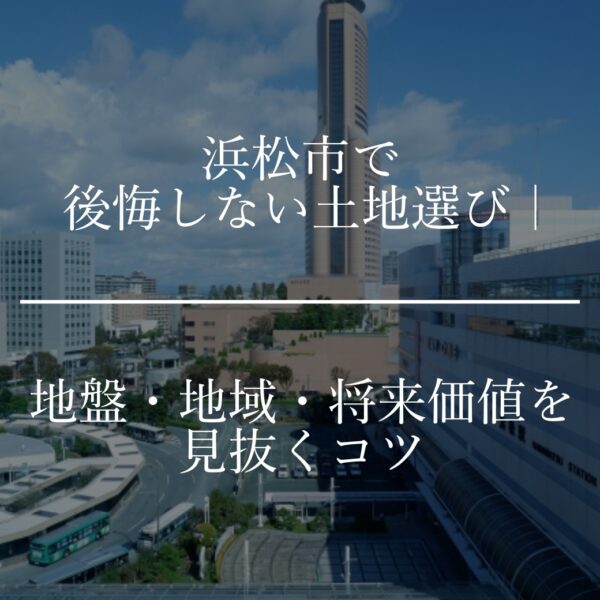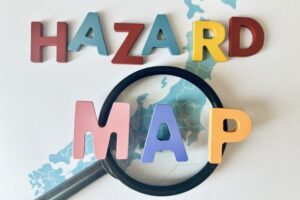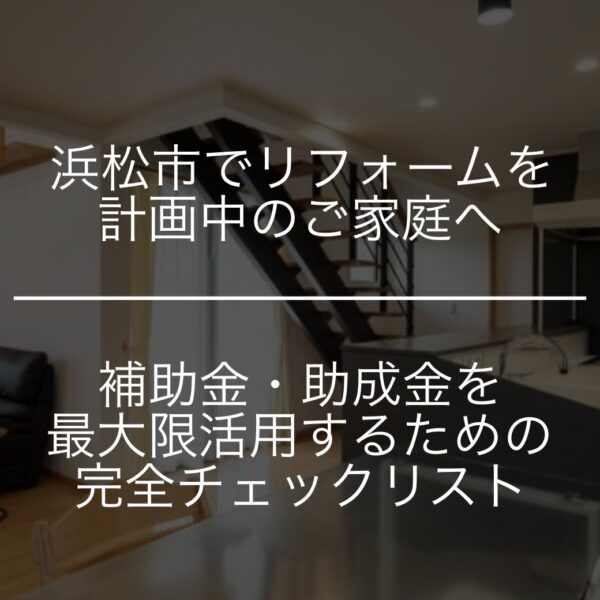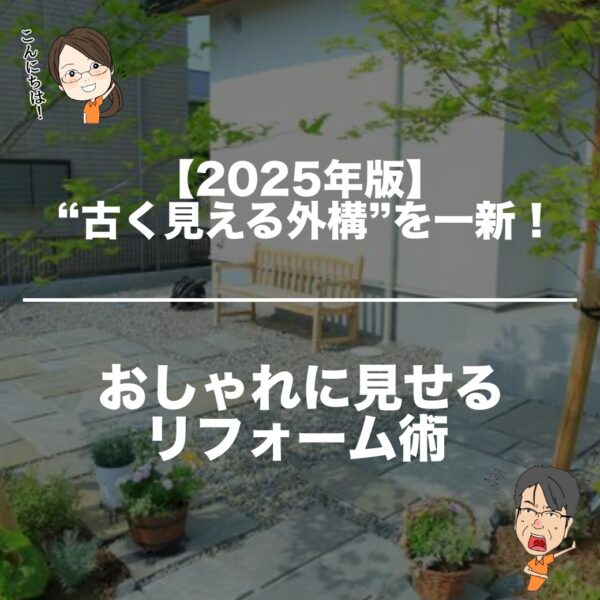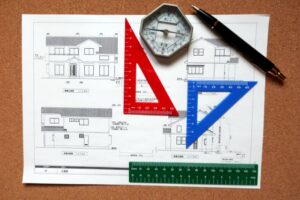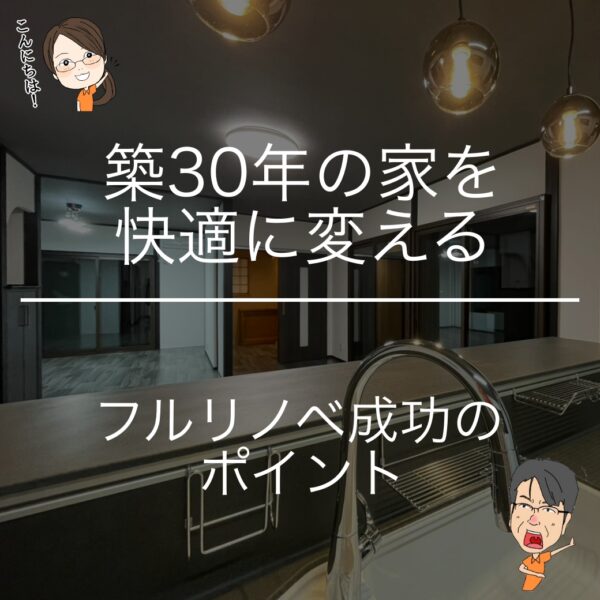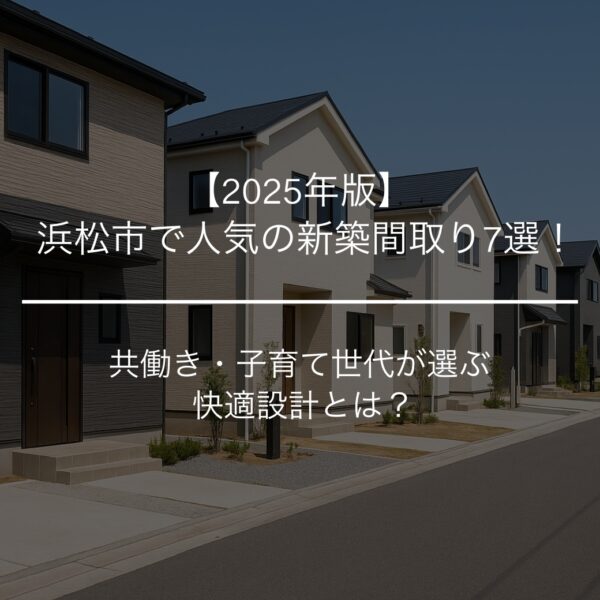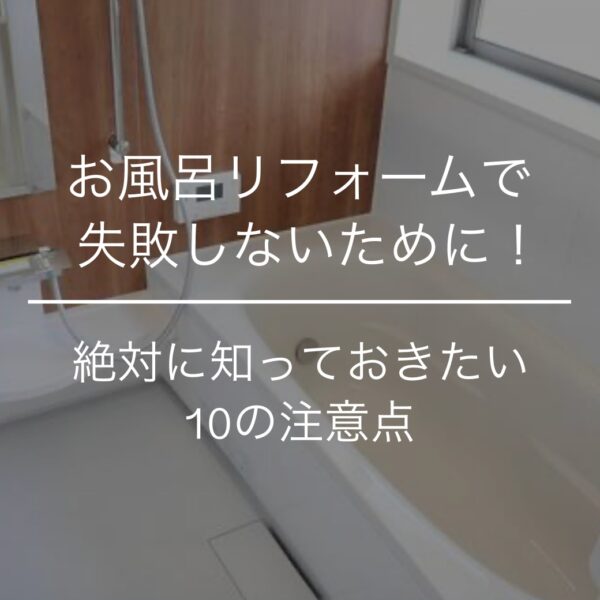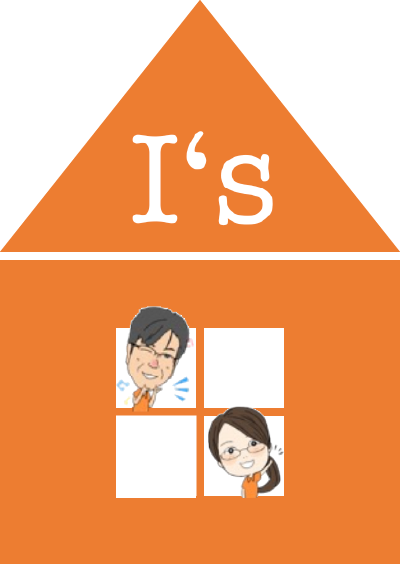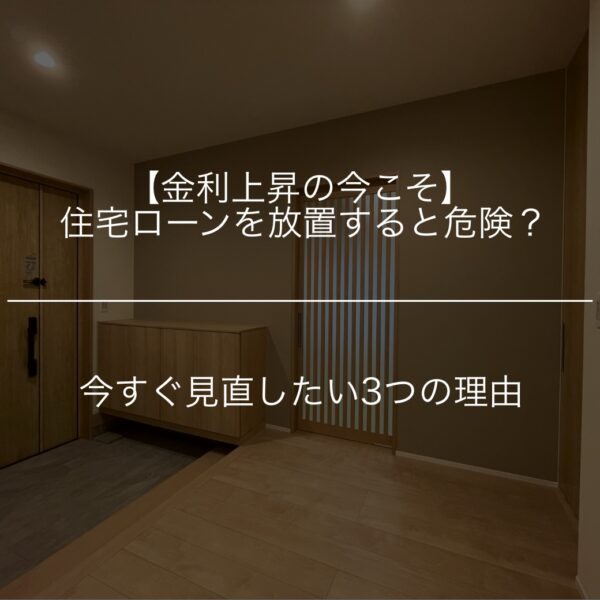
ここ数年、住宅ローンの金利がじわじわと上昇しています。
「うちは変動金利だからまだ大丈夫」と思っていませんか?実は、返済額が変わっていなくても、支払いの中身が“利息ばかり”になっていることがあります。
こうした状態を放置すると、知らないうちに家計の負担が増え、将来の資金計画に影響を及ぼすことも。
住宅ローンは、人生でもっとも長く関わる“お金の契約”です。借りたときの条件が永遠に続くわけではなく、金利情勢・家計状況・ライフプランの変化に合わせて、定期的に見直すことが大切です。
今回は「住宅ローンを放置する危険性」と「見直すべき3つの理由」を、わかりやすく解説します。
理由①金利上昇で“元金が減らない”現象が起こる
変動金利では、半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額が調整されます。つまり、金利が上がっても5年間は毎月の返済額が変わらない仕組みです。この仕組みは一見安心に思えますが、実は注意が必要です。
金利上昇時は、同じ返済額の中で「利息」が増え、「元金」がほとんど減らなくなります。これが続くと、住宅ローンの残高が思うように減らず、完済までの道のりが長引いてしまうのです。特に金利上昇が続いた場合、返済総額が数百万円単位で増えるケースもあります。

理由②借り換えを逃すと“チャンス損失”になる
住宅ローンの借り換えは、「今の金利」と「借り換え後の金利」の差が大きいほど効果があります。
たとえば、0.3%の金利差でも、35年ローンの場合は総支払額で100万円以上の差になることもあります。
しかし、このチャンスは永遠に続くわけではありません。金利が上がりきった後では、借り換えのメリットが薄れてしまうため、“タイミング”が非常に重要です。
特に、ローン契約から5年以上経っている方は、一度現状の金利条件を確認しておくことで、無駄な支払いを防ぐことができます。

理由③ 家計とライフプランの変化にズレが生じる
住宅ローンを組んだ当時は、家族構成や収入も安定していたかもしれません。しかし、教育費の増加や老後資金の準備、転職などによって家計は変化していきます。
こうした“人生の変化”に合わせてローンを見直さないと、返済が家計を圧迫する原因になりかねません。
ローンの見直しでは、返済期間の延長や金利タイプの変更、繰上返済などの方法があります。
ライフプラン全体を踏まえて、どの選択がもっとも無理のない形かを判断することが大切です。
建築を依頼した住宅会社に相談し、シミュレーションを行うことで、より安心して将来設計ができます。

住宅ローン借り換え相談会
毎月の返済をもっとラクに、将来の安心を手に入れませんか?
毎月の支払い、少しでも軽くできたら…
「住宅ローンの返済が家計の大半を占めている」
「金利が上がるニュースを見ると不安になる」
そんなお声を最近よく耳にします。
実は、今のローンを“見直す”だけで月々1万円以上支払いが軽くなるケースも珍しくありません。
さらに、総返済額が100万円以上変わることもあるのです。
今回開催する「住宅ローン借り換え相談会」では、
専門の住宅FPが今の金利・将来の金利動向・あなたのライフプランをもとに、
最適な返済プランをご提案いたします。
無理な勧誘は一切ありません。
「うちも借り換えたほうがいいのかな?」と気になったタイミングで、
お気軽にご参加ください。
【こんな方におすすめです】
-
月々の支払いを少しでも減らしたい方
-
固定金利から変動金利に変えるか迷っている方
-
変動金利のままで大丈夫か不安な方
-
住宅ローンを組んでから5年以上経っている方
-
教育費や老後の資金も考えて、将来に備えたい方
「今のローン内容を見直したいけれど、どこに相談したらいいかわからない…」
そんな方にこそ、一度参加していただきたい相談会です。
【相談会でわかること】
-
いま借り換えをするべきかどうか
→ 金利だけでなく、保証料・諸費用も含めて「得か損か」を数値で比較します。 -
どの銀行・金利タイプが合っているか
→ メガバンク、ネット銀行、地方銀行などを比較し、あなたに最適な選択を一緒に考えます。 -
将来の家計にどんな影響があるか
→ 教育費や老後資金のシミュレーションも行い、安心して返済を続けられるかを確認します。 -
借り換え以外の選択肢
→ 繰上返済・金利タイプ変更・返済期間の見直しなど、他の手段もアドバイスします。
【相談会の流れ】
-
ご予約
お電話でのご予約ですとスムーズにご案内できます。
フリーダイヤル:0120-806-006 -
下記URLよりフォームにて、ご希望の日時を選択してお申し込みください。
(平日・土日とも開催。お子様連れでもOKです) -
ヒアリング
現在のローン内容や家計の状況をお伺いします。
事前にローン明細や金利のわかる書類をご準備いただくとスムーズです。 -
シミュレーション
金利差・期間・諸費用をもとに、借り換え後の毎月の返済額を具体的に比較。
「どれだけ変わるのか」が一目でわかります。 -
アドバイス・質疑応答
あなたのライフプランに合わせた最適な返済方法をご提案します。
無理に借り換えを勧めることはありません。安心してご相談ください。
【参加者の声】
「思っていたよりも簡単にシミュレーションできて驚きました!」
「ネット銀行の方が安いと思っていましたが、意外な結果に!」
「教育費とのバランスを見直すきっかけになりました」
多くの方が「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃいます。
住宅ローンは“長く付き合うもの”だからこそ、定期的な見直しが大切です。
【開催概要】
-
開催日:毎週土日(平日をご希望の方はご相談ください)
-
時間:10:00〜17:00(1組60分〜90分)
-
会場:アイズホーム本社事務所
〒433-8119
静岡県浜松市中央区高丘北3丁目1-17 -
参加費:無料(完全予約制)
-
持ち物:ローン返済予定表・源泉徴収票(任意)
※お子様と一緒のご来場も大歓迎です。
【お申し込みはこちら】
以下のフォームに必要事項をご入力ください。
折り返し、スタッフより日程確認のご連絡を差し上げます。
お問い合わせフォーム:https://is-h.jp/inquiry
ご希望日時(第1〜第3希望まで)
お問い合わせフォームの詳細記入欄にご希望日時(第1〜第3希望まで)をご記載ください。
\ まずはお気軽にご相談ください! /
【最後に】
住宅ローンの借り換えは、「家計の見直し」と「将来の安心」を得るチャンスです。
何となく不安を感じながら過ごすよりも、
一度プロに相談して“現状を知ること”から始めてみませんか?
あなたとご家族様が、安心して笑顔で暮らせる未来のために。
私たちはその第一歩をサポートいたします。